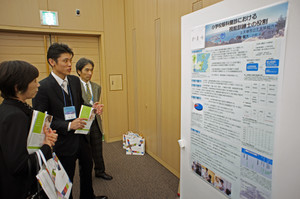- ホーム
- 病院ブログ
病院ブログ
現在、2月3日より各職員を8日間に分けて消防署職員の方をお招きし、救急蘇生訓練が行われています。業務終了後の1時間弱という時間ながら全員参加で訓練に励んでおります。
私達病院職員たる者にとって、救急蘇生法とは必ず覚えておかなければいけないものであり、当たり前にこなしておかなければいけないことでもあります。院内に限らず、プライベートでも誰かが倒れていたなら率先して、即座に対応できるような人物でありたいです。
病院職員という立場上、蘇生法を知らないということはおかしなことでもありますので当院でも数年前から毎年行っております。


私達は、直接ではないにしろ患者様のお命、お体を間接的に預かる、看る立場にあります。
このような救急蘇生法にしても私達に出来ることは限られますが、病院職員としてふさわしい対応の方法を知っておくだけでも当院を受診される方に安心感を与えられたらと思います。
Y.H
平成25年12月5日(木)院内で患者急変時の訓練を行いました。外来、2病棟、3病棟、4病棟、5病棟、きららの里と起こりうる場面に応じて様々なシチュエーションで行われました。
訓練は発見→呼びかけ→ドクターコール→心肺蘇生(胸部圧迫、AED)→医師が到着するまでの間の時間を計りながら行われました。
私はカメラマンとしてその訓練風景を拝見させていただきましたが、患者家族役の方もわが身のように演技をしていて本当の訓練ではなく実際起きているのではないかというくらいの錯覚すら覚えました。駆けつけた看護師の皆さんも訓練だからとは思わずに必死に蘇生訓練をされていました。
今回は各部署別の写真を掲載いたします。
内科外来
2病棟
3病棟
4病棟
5病棟
きららの里
必死さが伝わってきます。訓練時同様、実際の現場に立ち会った場合も対処は大丈夫でしょう。
練習に勝るものはありません。やはり日頃からこのような訓練を行い、いつ何時起こってもいいような体制を築き上げることこそ大切なことといえるでしょう。(Y.H)
- 最新記事